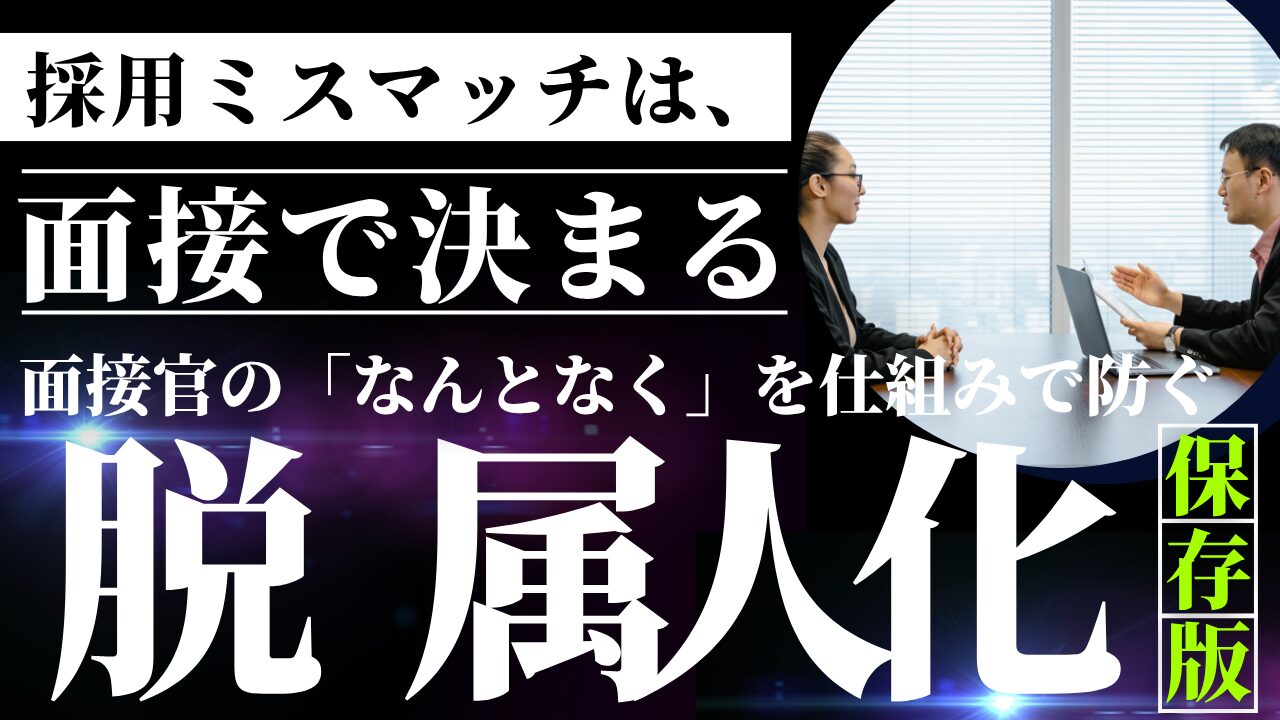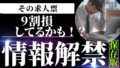「面接官Aさんは高評価なのに、Bさんは低評価。一体どちらの意見を信じればいいんだ…」
「最終面接まで進んだのに、なぜかミスマッチが起きてしまう」
採用の選考過程で、このような「評価のばらつき」に頭を悩ませた経験はありませんか?
その原因は、面接官個人の性格や能力の問題だけではなく、誰の心にも潜む「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」の仕業かもしれません。
この記事では、行動経済学の知見を元に、採用の公平性を脅かすバイアスの正体を解き明かし、その具体的な対策として注目される「構造化面接」の導入方法を、明日から実践できるレベルで分かりやすく解説します。
なぜ評価はブレるのか?面接官を悩ませる「アンコンシャス・バイアス」の正体
あなたも持っている「無意識の偏見」
アンコンシャス・バイアスとは、自分自身では気づいていない「ものの見方や捉え方の歪み・偏り」のことです。これは決して特別なものではなく、脳が効率的に情報を処理するために、過去の経験や知識から無意識にショートカットしているだけの、ごく自然な働きです。
しかし、採用面接という「人」を評価する場において、このバイアスは意図せず不公平な判断を生み出す原因となってしまいます。
面接で特に注意したい3つのバイアス
採用面接では、特に以下の3つのバイアスが働きやすいと言われています。
- 類似性バイアス 自分と出身大学や経歴、趣味が同じといった共通点がある候補者に対し、無意識に親近感を覚え、能力を高く評価してしまう心理。
- ハロー効果 「有名大学出身」「プレゼンが非常に上手い」といった一つの優れた特徴に引きずられ、他の評価項目まで「きっと優秀だろう」と高く評価してしまう心理。逆のパターン(一つの欠点が全体を悪く見せる)も存在します。
- 確証バイアス 「この候補者は良さそうだ」という第一印象を持つと、その印象を裏付ける情報ばかりを探し、それに反する情報を軽視・無視してしまう心理。
これらのバイアスは無意識に働くため、「気をつけよう」という心構えだけでは防ぐことができません。必要なのは、バイアスが入り込む隙を与えない「仕組み」です。
主観を排除する処方箋「構造化面接」の導入ガイド
そこでおすすめしたいのが、Google社をはじめ多くの企業で導入されている「構造化面接」です。
構造化面接とは?「評価のモノサシ」を全員で揃える技術
構造化面接とは、あらかじめ「評価する項目」と「質問する内容」を具体的に決め、すべての候補者に対して同じ手順・基準で実施する面接手法です。
面接官の経験や勘に頼るフリートーク形式の面接とは対照的に、評価のモノサシを統一することで、面接官個人の主観やバイアスの影響を最小限に抑え、候補者の能力を客観的かつ公平に評価することを目指します。
明日からできる!構造化面接3つのステップ
- 【Step1】評価基準を決める まず、そのポジションで成果を出すために不可欠な能力(コンピテンシー)は何かを定義します。「問題解決能力」「主体性」「チームワーク」など、具体的で測定可能な項目を3〜5つに絞り込みましょう。
- 【Step2】質問を統一する 次に、Step1で決めた評価基準を測るための質問リストを作成し、全候補者に同じ質問をします。特に有効なのが、過去の行動を問う質問です。
- 質問例(問題解決能力を測る場合): 「これまでの仕事で、最も困難だった課題と、それをどのように乗り越えたかについて具体的に教えてください」
- 【Step3】評価シートを作成する 評価基準ごとに「5:非常に優れている」〜「1:期待を下回る」といった5段階評価の基準(評価シート)を作成します。面接官は面接中にメモを取り、終了後にこのシートに基づいて点数化することで、印象論ではない客観的な評価が可能になります。
もう一つの選択肢「ブラインド採用」とは?
書類選考の段階でバイアスを排除する方法として「ブラインド採用」も注目されています。
これは、履歴書やエントリーシートから、氏名、性別、年齢、顔写真といった、業務遂行能力とは直接関係のない個人情報を隠して選考を行う手法です。
メリットは、先入観を強制的に排除できるため、これまで見過ごしていたかもしれない優秀な人材を発掘できる可能性がある点です。一方で、導入に手間がかかることや、面接に進めば結局バイアスがかかる可能性がある点には注意が必要です。構造化面接と組み合わせることで、より効果を発揮するでしょう。
まとめ:公平な採用が、会社の未来を創る
面接官によって評価がブレてしまうのは、誰にでもある「アンコンシャス・バイアス」が原因です。そして、その最も効果的な対策が、評価のモノサシを統一する**「構造化面接」**という仕組みの導入です。
- 評価基準を明確にし、
- 全員に同じ質問を投げかけ、
- 統一された評価シートで判断する。
完璧な導入が難しくても、まずは一つのポジションから評価基準を言語化してみるだけでも、採用の質は大きく変わるはずです。
公平な選考プロセスは、候補者からの信頼を高め、採用のミスマッチを防ぎ、ひいては会社の未来を創る土台となります。ぜひ、あなたの会社でも「なんとなく」の評価から脱却する一歩を踏み出してみてください。