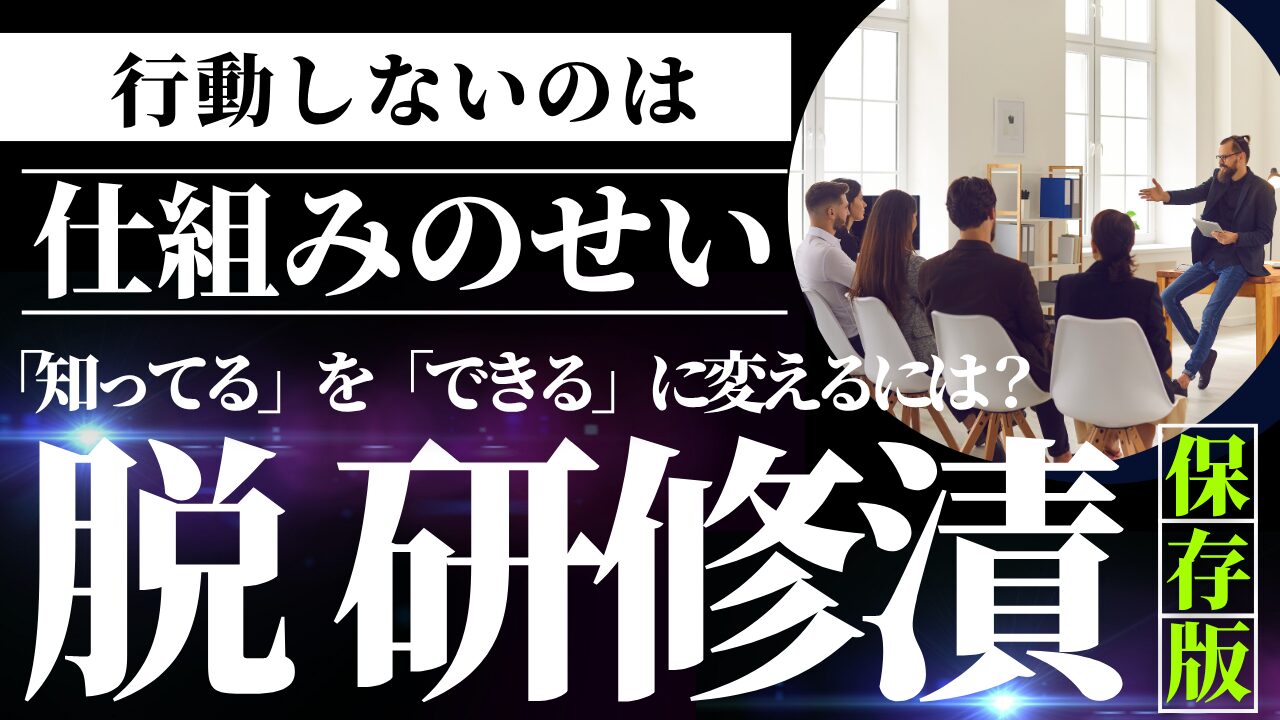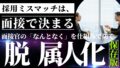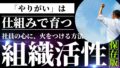「時間とコストをかけて研修を実施したのに、現場では何も変わっていない…」
「研修中はやる気だったはずの社員が、日常業務に戻るとすっかり元通り…」
人材育成に携わる方なら、一度はこうした「研修やりっぱなし」問題に直面したことがあるのではないでしょうか。
その原因は、研修内容の質や、社員の意欲が低いことにあるとは限りません。多くの場合、私たちは「将来の大きな成果」よりも「目先の楽」を優先してしまう、人間の**「現在志向バイアス」**という心理的なクセを見過ごしているのです。
この記事では、行動経済学の知見を活かし、この厄介なバイアスを乗り越え、研修で学んだ内容を「知っている」から「できる」へと変える、具体的な2つのコツを解説します。
なぜ行動は変わらない?研修効果を阻む「現在志向バイアス」の罠
現在志向バイアスとは、「将来得られる大きなリターンよりも、すぐに手に入る小さなリターンを過大評価してしまう」という心のクセです。
「研修で学んだことを実践すれば、半年後にはきっと大きな成果が出る」と頭では分かっていても、「でも、今日は忙しいから明日からにしよう」「新しいやり方は面倒だから、とりあえず今まで通りで…」と、つい目先の楽な選択をしてしまう。これが、研修内容が現場で実践されない大きな理由です。
このバイアスに精神論で立ち向かうのは困難です。必要なのは、行動へのハードルを極限まで下げ、自然と「やってみよう」と思える「仕組み」をデザインすることです。
コツ1:【マイクロハビット】「これならできる」から始める小さな成功体験
いきなり大きな目標を掲げても、現在志向バイアスが「面倒くさい」という気持ちを増幅させ、行動にブレーキをかけてしまいます。
そこで有効なのが「マイクロハビット(非常に小さな習慣)」という考え方です。行動の第一歩を、意志の力が必要ないくらい小さく分解し、「これならできる」という成功体験を積ませるのです。
研修後の「最初の一歩」をデザインする具体例
- NG例:「研修で学んだ営業手法を、明日からすべて実践してください」
- OK例:「研修で学んだアプローチトークのうち、まず1つだけ、明日の朝一番の電話で使ってみてください」
- NG例:「新しいフィードバック手法を、次の1on1で完璧にこなしてください」
- OK例:「次の1on1では、冒頭の5分間だけ、研修で学んだ『ポジティブな点から伝える』手法を意識してみてください」
ポイントは、行動を「タスク」ではなく「実験」と捉えさせること。「まず1つだけ」「5分だけ」という小さな成功体験は、「やればできる」という自己効力感を育み、次の行動へのモチベーションとなります。
コツ2:【ピア効果】「仲間の目」が行動を後押しする
一人で頑張り続けるのは大変ですが、誰かに見られている、仲間も頑張っているという状況は、行動を継続させる強い力になります。これが「ピア効果(同僚からの影響)」です。
研修を個人の学びで終わらせず、チームのイベントとして設計することで、互いに良い影響を与え合う環境を作り出せます。
行動を後押しする「環境」を作る具体例
- 実践報告会の設定 研修の1週間後などに、「研修で学んだことを1つ実践してみた結果」を共有する短い会を設定する。「報告しなければならない」という適度な強制力が、行動を促します。
- チーム内での目標共有 研修後、チームで「今週、研修内容を活かしてチャレンジすること」を一人ひとり宣言し合う。お互いの目標を知ることで、協力や声かけが生まれやすくなります。
- 専用チャットグループの活用 研修参加者だけのチャットグループを作り、「〇〇を試したら、うまくいきました!」「△△で苦戦してるんですが、どうしてますか?」といった実践報告や相談を気軽にできる場を作る。
まとめ:研修は「中身」だけでなく「デザイン」で決まる
研修効果が出ないのは、社員のせいでも、研修内容だけのせいでもありません。多くの場合、それは人間の「現在志向バイアス」を考慮しない「デザイン」の課題です。
- マイクロハビット: 行動のハードルを極限まで下げ、小さな成功体験を積ませる。
- ピア効果: 仲間との関わりの中で、行動を後押しする環境を作る。
研修を「知識をインプットする場」から、「行動のきっかけをデザインする場」へと捉え直すこと。ぜひ、次の研修企画から、この2つのコツを取り入れてみてください。